映画『午前4時にパリの夜は明ける』は、パリ西部に暮らすある家族の7年間を見つめた優しさに溢れた人間ドラマだ。
youtu.be1981年、パリ。長年不仲だった夫が家を出て行ったためエリザベートは初めて社会に出て働き始める。彼女が得た職は深夜放送のラジオ番組の仕事だった。
エリザベートはそこで出会った家出少女のタルラを自宅へ招き入れる。野宿をしようとしている彼女を放っておけなかったのだ。共に過ごすなかで「家族」はそれぞれの人生を見つめ直していく…。
『アマンダと僕』(2018)、『サマーフィーリング』(2015)のミカエル・アースが監督を務め、シャルロット・ゲンズブールがエリサベートを、ノエ・アビタが家出少女のタルラを演じる他、エマニュエル・ベアール、キト・レイヨン=リシュテル、メーガン・ノーサムらが出演している。
2022年・第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品作品。
目次
映画『午前4時にパリの夜は明ける』作品情報

2022年製作/111分/R15+/フランス
原題:Les passagers de la nuit
監督:ミカエル・アース 脚本:ミカエル・アース、モード・アメリーヌ、マリエット・デゼール 撮影:セバスティアン・ビュシュマン 美術:シャルロット・ドゥ・カドビル 編集:マリオン・モニエ 音楽:アントン・サンコー
出演:シャルロット・ゲンズブール、キト・レイヨン=リシュテル、ノエ・アビタ、メーガン・ノーサム、ティボー・バンソン、エマニュエル・ベアール、ロラン・ポワトルノー、ディディエ・サンドル、
映画『午前4時にパリの夜は明ける』あらすじ

1980年代、パリ。結婚生活が終わりを迎え、ひとりで子供たちを養うことになったエリザベートは、初めて社会に出て働き始める。
最初の仕事は初日でクビになり落ち込むエリザベートだったが、深夜放送のラジオ番組の仕事に就くことに。
リスナーたちが自身の境遇を語り、悩みを相談するという番組で、エリザベートはリスナーからの電話を司会者に取り次ぐ役目を与えられる。
ある時、まだ幼く見える少女がスタジオにやって来た。彼女はタルラと名乗り、自身について話し始めた。家出をして外で寝泊まりしているという。
まだ夜が明けない時間、仕事を終えたエリザベートはベンチに座ってカフェが開くのを待っているタルラをみかけ自宅へ招き入れた。
そんなタルラをエリザベートの子供たちも快く受け入れた。
ともに暮らすなかで家族はそれぞれ、自身が過ごしてきたこれまでの人生を見つめ直していく。
ティーンエイジャーの息子マチアスは、詩人になりたいという夢を持っていた。他の教科には興味が持てず、母に内緒で学校もさぼりがち。タルラと接するうちに次第に彼女に惹かれていく。
ある日、タルラと出かけたマチアスは誤ってセーヌ川に落ちてしまう。タルラも彼を助けようと川に飛び込み、ふたりはずぶ濡れの格好で、家に戻った。
濡れた服を脱ぎながら二人は抱き合って愛を交わした。しかし翌日、タルラは姿を消してしまう。
時は1988年。エリザベートはラジオの仕事の他に図書館でも働き、毎回大量に本を借りていく男性と知り合い恋に落ちる。
姉は独立し、マチアスはフィットネスクラブの清掃の仕事をしながら詩人を目指していた。
ある日、彼女たちはマンション内にタルラが倒れているのを発見する。
タルラは麻薬に手を出していた。エリザベートは、彼女を施設に入れた方が良いのか思案するが、マチアスはありえないと怒り出し、再び彼女たちはタルラを家に迎え、一緒に暮らし始める。
映画の好きなタルラは映画館で働き始め、落ち着いたように見えたが、またクスリに手を出してしまう。マティウスは彼女に愛を告白するのだが・・・。
映画『午前4時にパリの夜は明ける』の感想・評価
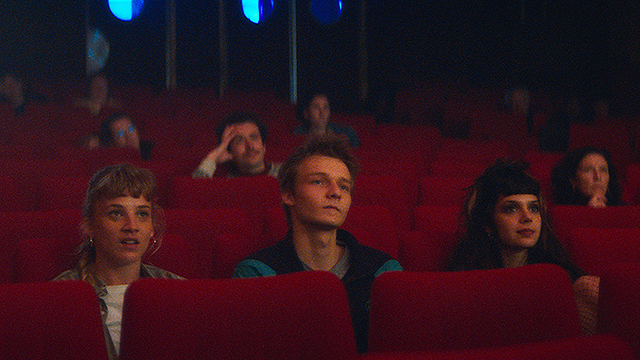
1981年5月10日、フランソワ・ミッテランが大統領選挙に勝利し、興奮した若者たちは夜の街に繰り出し、喜びを爆発させていた。
そこにシャルロット・ゲンズブール扮するエリザベートとその家族が乗った車が通りかかる。車は路上の若者たちの間をゆっくりと進み、エリザベートは若者たちと目を合わせて喜びを分かち合う。
このように希望で始まった1980年代のパリ。1981年、1984年、1988年の3つの年を軸に、エリザベートとその子どもたちの、それぞれの7年に渡る人生の変遷が描かれて行く。
1984年、夫が出ていったため、悲しみと不安で一杯のエリザベートは、深夜ラジオの仕事につき、懸命に第二の人生を歩み始める。
深夜ラジオは、眠れない人のためのネットワークの役割を果たしており、エリザベート家がタルラという少女と出合うきっかけを作ったのもラジオだった。
スタジオにやって来たあと行く場所もなく、まだ明けぬ夜のベンチに座りカフェが開くのを待っていたタルラをエリザベートは迷うことなく自身の家に導くのだ。
エリザベートと子どもたちの温かな心が画面から溢れんばかりだ。それはミカエル・アースの穏やかな語り口のせいでもあり、シャルロット・ゲンズブールを始めとする役者陣の素晴らしい演技の賜でもある。
何より、こんなに暖かく優しい映画が作られ存在していること自体に深く感動してしまう。光煌めくパリの摩天楼や夜明けの薄明かりの光景を捉えるカメラの視線もとても優しい。
原題の「Les passagers de la nuit」は「夜の乗客」という意味。エリザベートが担当するラジオ番組名でもある。番組に電話してくる人々は「乗客」と呼ばれるのだが、実際、タルーラは「乗客」という呼び名が相応しいだろう。
なぜなら、初めて彼女が登場するシーンで彼女は、パリの地下鉄のマップとオーバーラップしていたからだ。
マップの前に立った彼女がマップの路線に手を当てるとその路線の駅を示す丸い部分が光り出す。手を動かすたびに光も動く。その光を見ていると、彼女はどこにでも行けそうに思えてくる。
とはいえ、彼女が背負っているものは思った以上に重く、当然のごとく現実は厳しい。それでも彼女がエリザベート家の「乗客」だった日々は彼女が生きていく上での大きな糧になるだろうと素直に思える。
そんなタルーラを通して、ミカエル・アースは映画への熱い思いを綴っている。
タルーラは映画館に忍び込むことで、居場所を確保し、寒さを凌ぎ、映画を観ることで救われてきた人物なのだ。
この映画館ではジャック・リヴェットの『北の橋』やエリック・ロメールの『満月の夜』などが上映されており、25歳で亡くなったパスカル・オジェへの想いが溢れ出す。
80年代を賑わせた音楽が多数使われているのも堪らない。Lloyd Cole and the Commotionsの”Rattlesnakes”、Televisionの” MarqueeMoon”やHeavenlyの”P.U.N.K.Girl"、The Pale Fountains の”Pacific Street”といった曲がノスタルジックにメランコリックに響き、映像を彩っている。
また、時折はさまれるパリの風景を撮った淡い色感の少しざらついたような映像は、本当に80年代に撮ったものなのか、はたまた現在のパリを撮ったものなのか定かではないが、いずれにしてもそのホーム・ムービーを彷彿させるような淡い色合いの映像からは80年代の空気を感じることができる。
それにしてもシャルロット・ゲンズブールの素晴らしさはどうだろう! あえて茨の道を行くことを選ぶ子どもたちのことを心配しながらも、彼らを大人と認めて自身も成長していく姿を鮮やかに演じている。その笑顔は本当に優しく美しい。
タルーラを演じたノエ・アビタのまだあどけなさが残る佇まいと大きな瞳も忘れがたい。
ミカエル・アース監督はそんな彼女たちにそっと寄り添い、それぞれの奮闘に温かい眼差しを向けるのだ。